<< back | next >>
| 1.冒頭挨拶 |
| 2.学会の軌跡 |
| 3.学会の役割とは |
| 4.学会の課題 |
| 5.学会の将来 |

|
1952(昭和27)年4月28日に46名の設立発起人の名で「日本図書館学会設立の趣旨」が発表され、翌1953年6月4日に国立博物館講堂において第1回総会が開催されました。
初代の会長海後宗臣氏により作られた「日本図書館学会規約」では、目的として「本会は、わが国図書館学会の総合学会として図書館学の進歩発展に寄与すること」を掲げておりました。
「堅実で効果的な図書館学研究の足場を築くため既設の図書館関係団体の持つ研究機能を結集して、一本に」することが学会設立の大きな目的でありました。
そのため、会員資格を「図書館関係の団体に所属している研究者」と限定することが考えられていましたが、結局は、個人会員の入会を認めることになりました。
 翌年、すなわち1954年には、学会誌を創刊、研究発表17件の総会が開催され、今日に続く学会活動の柱が作られました。
翌年、すなわち1954年には、学会誌を創刊、研究発表17件の総会が開催され、今日に続く学会活動の柱が作られました。
本日配布しております『記念誌』掲載の根本彰氏と三浦太郎氏による『日本図書館情報学会20年略史』では、日本図書館学会の設立の背後には、第二次大戦後に起きた、米国のライブラリアンシップの導入、司書および司書補の講習を大学で行うことを明記した図書館法の制定、さらに日本図書館研究会、IFEL図書館学会、東京大学図書館学会などの相次ぐ設立など図書館学の制度化があったと指摘されています。
図書館学の総合学会を目標として設立された日本図書館学会は、1956年の規約改正で「わが国図書館学会の総合学会として」という文言を削除し、普通の学会へと転換いたしました。
その後、財政的な問題もあり、一時、学会活動の停滞がみられましたが、創立20周年を契機として、今日まで続く、学会賞、奨励賞の授与、論集の刊行、文献目録の編集などの事業が開始され、運営は軌道に乗り、徐々に会員数を増やしつつ現在に至っております。
そして、1998年には、定例総会において学会名称の変更に関する議題が採択され、同年10月1日から学会の名称を「日本図書館学会」から「日本図書館情報学会」と変更いたしました。
本学会では、設立以後20年の間は、毎年秋に総会と研究大会が開催されておりましたが、1972年以後、議決機関である総会は、年度はじめに通信総会として開かれるようになり、研究大会から分離されました。研究大会は、設立以来、会員の所属する大学を中心に開催されてきました。
最近では、関東とそれ以外の地域で交互に研究大会を開催しておりますが、開催をお引き受け下さった大学では、いずれも堅実で心のこもった見事な運営をなさっておられます。
研究発表の場として、もう一つ1991年より設けられた毎年5月に開催する春季研究集会があります。
これは、それまで個人研究発表の場として年8回ほど開かれていた月例会に変わるものであります。
春季研究集会は、当初、若手研究者の発表の場となっておりましたが、発表件数が次第に増加し、現在では、秋の研究大会と同等に位置づけられております。
これまで研究大会、月例会、春季研究集会の開催にあたり、会場をご提供下さった機関、また、そのお世話に当たられた方々に、改めてここで深く感謝いたします。
| 総会・研究大会開催校 | |||||
| 1 | 東京博物館 | 2 | 東京大学 | 3 | 京都大学 |
| 4 | 広島大学 | 5 | 東京大学 | 6 | 新潟大学 |
| 7 | 九州大学 | 8 | 慶應義塾大学 | 9 | 東洋大学 |
| 10 | 國學院大学 | 11 | 天理大学 | 12 | 早稲田大学 |
| 13 | 日本大学 | 14 | 図書館短期大学 | 15 | 名古屋市教育館 |
| 16 | 鶴見女子大学 | 17 | 亜細亜大学 | 18 | 大阪府立青少年会館 |
| 19 | 国士舘大学 | 20 | 図書館短期大学 | 21 | 別府大学 |
| 22 | 東京学芸大学 | 23 | 立教大学 | 24 | 大阪市立中央公会 |
| 25 | 共立女子大学 | 26 | 慶應義塾大学 | 27 | 鶴見大学 |
| 28 | 武蔵野女子大学 | 29 | 大東文化大学 | 30 | 武庫川女子大学 |
| 31 | 東洋大学 | 32 | 専修大学 | 33 | 椙山女学園大学 |
| 34 | 国学院大学 | 35 | 法政大学 | 36 | 北海学園大学 |
| 37 | 図書館情報大学 | 38 | 桃山学院大学 | 39 | 中央大学 |
| 40 | 海の中道ホテル | 41 | 相模女子大学 | 42 | 東海大学 |
| 43 | 天理大学 | 44 | 駿河台大学 | 45 | 同志社大学 |
| 46 | 青山学院大学 | 47 | 大阪市立大学 | 48 | 亜細亜大学 |
| 49 | 愛知淑徳大学 | 50 | 明星大学 | 51 | 筑波大学 |
 学会における研究事業のもう一つの柱が学会誌の刊行であります。
学会における研究事業のもう一つの柱が学会誌の刊行であります。現在の『日本図書館情報学会誌』の前身にあたる『図書館学会年報』は、1954年に創刊されました。
創刊から二十数年間は、財政的な問題もあり、定期的な刊行もままならない状態で、1号も刊行されない年がありました。
 しかし、次第に体制が整い、1977年からは文部省科学研究費の出版補助を受けることになり、また、査読制度も導入されました。
しかし、次第に体制が整い、1977年からは文部省科学研究費の出版補助を受けることになり、また、査読制度も導入されました。学会誌の改革については、1971年から1985年までの間、編集委員長をお務めになった石山洋氏のご尽力に負うところが大であります。
現在の学会誌は、自由投稿制度と査読制度をとり、会員に研究発表の機会を提供すると共に、業績評価の場として機能しております。
 1982年度から『論集・図書館学研究の歩み』が、毎年1集ずつ刊行されはじめました。
1982年度から『論集・図書館学研究の歩み』が、毎年1集ずつ刊行されはじめました。これは、実務から研究にわたる現時的な主題に関して、公募と依頼によって論文を集めたもので、研究大会におけるシンポジウムと連動しておりました。
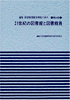 第13集から『論集・図書館情報学研究の歩み』と改称されましたが、2000年刊行の第20集で終了しました。
第13集から『論集・図書館情報学研究の歩み』と改称されましたが、2000年刊行の第20集で終了しました。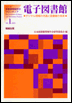 そして、2001年からは、『シリーズ・図書館情報学のフロンティア』として模様替えし、毎年、研究委員会のもとで編集、刊行されております。
そして、2001年からは、『シリーズ・図書館情報学のフロンティア』として模様替えし、毎年、研究委員会のもとで編集、刊行されております。図書館情報学会の重要な事業として、『文献目録』と『用語辞典』の編集があります。
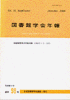 1973年から図書館学に関する主題書誌である『図書館学年次文献目録』の編集が始まり、『図書館学会年報』に掲載され、後には別巻となり、1992年まで続きました。
1973年から図書館学に関する主題書誌である『図書館学年次文献目録』の編集が始まり、『図書館学会年報』に掲載され、後には別巻となり、1992年まで続きました。これは20年間にわたり編集を担当された深井人詩氏のご尽力によるものであります。
その後は、学会内に「図書館情報学文献目録委員会」を設置し、入力規則、シソーラス、分類表を整備し、文献目録データベースとして作成しております。
科学研究費の研究成果公開促進費の補助を受け、現在まで18,990件を入力し、CD-ROMとウェブで検索サービスを提供しております。
学会創立20周年の際に、「図書館学事典」の刊行が企画され、以後同事典編集委員会の手で編集作業が行われましたが、原稿が集まらず、1983年にこの事業は中止されました。
一方、1990年から「図書館情報学用語 標準化の調査研究」に関して、学会に対して科学研究費補助があり、3年間にわたり当時の岩猿敏生会長を中心に作業を行いました。
 その成果をもとに、1997年に『学術用語集 図書館情報学用語編』が刊行されました。
その成果をもとに、1997年に『学術用語集 図書館情報学用語編』が刊行されました。 そして、学術用語集の収録語から選択した項目に解説をつけた『図書館情報学用語辞典』を同年に、その改訂版である第二版を2002年に刊行いたしました。
そして、学術用語集の収録語から選択した項目に解説をつけた『図書館情報学用語辞典』を同年に、その改訂版である第二版を2002年に刊行いたしました。これは、収録予定項目を会員に示し、原稿を公募するという方式をとっております。
創立20周年を期に制定された会員顕彰制度であります学会賞と奨励賞では、2002年度までに10件の学会賞授賞著作と28名の奨励賞授賞者を出しています。
また1980年度から研究助成金の交付を行ってまいりました。
以上、この50年間にわたる本学会の活動と事業を概観いたしました。
さて、日本図書館情報学会は、2003年10月15日現在で、個人会員は702名に達しております。
この間、会員数は、初期に停滞があるものの、現在は、順調に増加傾向を示しております。
会員の居住地は、関東、関西、東海を中心とし、ほぼ全都道府県意にわたっております。
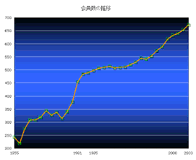 |
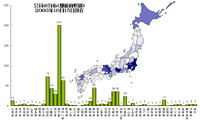
|
![]()
<<< 創立五十周年記念ニ戻ル